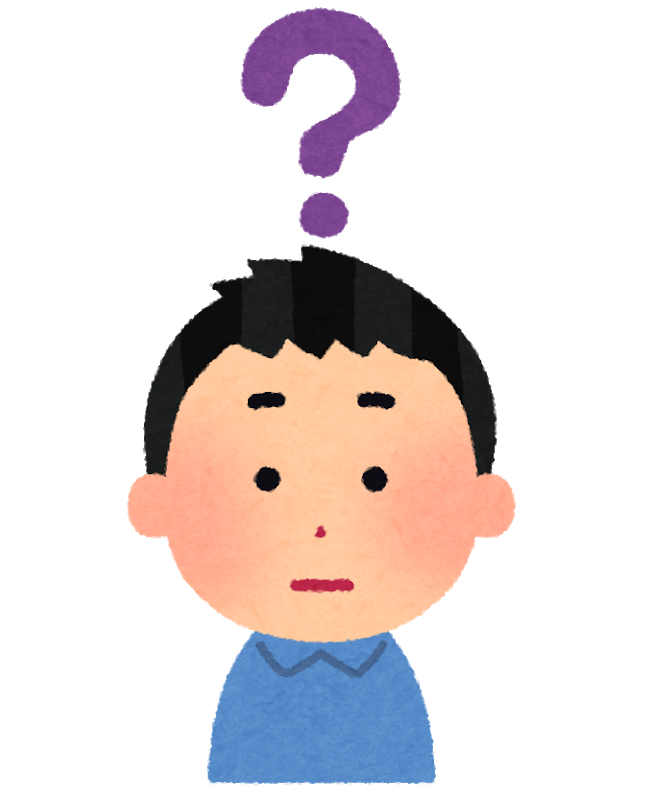このような疑問やお悩みをお持ちの患者様が多く来院します。
これは粘液嚢胞(ねんえきのうほう)と言います。
大きさは5mm程度で、治療は通常必要ありませんが、大きさや症状によっては治療が必要となる場合があります。
粘液嚢胞の治療方法について知りたい方はこちらもお読みください。
それでは、粘液嚢胞についてや口の中のできものなどについて解説をしたいと思います。


口の中には大唾液腺の耳下腺、顎下線、舌下腺、そしてそれ以外に米粒大くらいの大きさの無数に見られる小唾液腺があります。
粘液嚢胞とは、その唾液腺がふさがって唾液が溜まり、多くの場合は透明か青みがかったピンク色で、柔らかく、滑らかで、丸状またはドーム型に膨らんできます。
主に下唇の粘膜や頬の粘膜、舌の下、口の底にできます。口の底にできるものはガマ腫と呼ばれています。
下唇を噛む癖なども粘膜を傷つける原因となるの好発部位は下唇ですが、粘液がある所はどの部位にもできます。
引用元 J-STAGE 口腔病学会雑誌 口腔粘液嚢胞の臨床的ならびに組織学的研究
発生部位別では口唇 が339(49.49%)で 最も多く、以下、口底の260例(37.96%)、舌 の46例(6.72%)、頬粘膜の34例(4.96%)、口蓋および臼歯腺部のそれぞれ3例(0.44%)の順であり、粘液瘤に限ると、口唇79.76%、舌10.82%、頬粘膜8.0%口蓋および臼歯腺部 それぞれ0.70%の分布であった
大きさは5mm程度で、硬くならず痛みはほとんどありません。
治療は通常必要ありませんが、大きさや症状によっては治療が必要となる場合があります。
誤って唇や頬の内側などを噛んでしまったり、ぶつけてしまったり、ほとんどは外傷性の場合が多いです。
もしくは唇を吸う癖のある場合も原因の1つと考えられます。
また、口内炎などで粘膜が傷ついてしまう場合や、虫歯などで歯が鋭利になったまま放ってしまい、粘膜が傷付いてしまう場合も粘液嚢胞の原因になってしまいます。
これらの傷が治るときに、唾液を出す管が詰まってしまうことによって粘液嚢胞になると考えられています。
粘液嚢胞は潰れて治ってしまう事が多いですが、繰り返していくうちに繊維化して硬くなり、丸い形になってだんだん大きくなってしまいます。

粘液嚢胞と口内炎、口唇ヘルペスの違いは何ですか?
| 粘液嚢胞 | 口内炎 | 口唇ヘルペス | |
| 原因 | 外的要因(ぶつけた、咬んでしまったなど) | ストレスや免疫力低下、外的要因、ウイルス感染など様々である | ヘルペスウイルスによって引き起こされる感染症。免疫力低下で現れる |
| 症状 | 大きさは5mm程度で、硬くならず痛みはほとんどない ただし、再発を繰り返すと繊維化して硬くなるこもある | 口腔内の粘膜にできる小さな潰瘍で、痛みやしみる感じの症状 | 水疱(水ぶくれ)や潰瘍(ただれ)が特徴的な症状 |
| 好発部位 | 粘膜がある所はどこでもできる | 口唇の裏、舌の辺縁、頬粘膜 | 口唇 |
| 治療法 | 手術やレーザー治療などで 摘出する | 塗り薬やうがい薬を使用する 外的要因であれば歯科治療を行う | 抗ウイルスの内服薬を服用する 家族間の感染が多いのでタオルなどの共有は避ける |
- 粘液嚢胞は自然治癒しますか?
- 粘液嚢胞を放置しても自然治癒することは稀であり、硬さが軟らかくなっていく場合でも、完全な治癒に至ることは難しいと言えます。
- 粘液嚢胞は放置してたらどうなりますか?
- ほとんどの場合、放置すると嚢胞は徐々に大きくなる傾向があります。
放置せずに歯科医院での適切な治療を検討することが重要です。小さいうちに適切な対処をすることで、症状の悪化や再発を防ぐことができます。
- 粘液嚢胞は自分で潰すとどうなりますか?
- 潰すと内溶液が漏れて少しの間は小さくなりますが、また液がリークし、溜まって大きくなります。繰り返すと繊維化して固くなってきます。自分で潰したり触ったりするとそこから感染を起こす可能性もあるのでオススメできません。
- 粘液嚢胞を自分で潰してしまいました。応急処置などはありますか?
- あまり触ったりせず、早めにクリニックへ受診して下さい。
- 粘液嚢胞は何科で診てもらえますか?
- 粘液嚢胞は口の中に出来るものなので基本的には歯医者で診てもらえます。
粘液嚢胞の治療は手術になりますので口腔外科の受診をおすすめします。
- 粘液嚢胞のできやすい年齢はありますか?
- 口腔粘液嚢胞は、30 歳未満の人が最も多く罹患しますが、あらゆる年齢層が罹患する可能性があります。
3歳から20歳までの人々が症例の70%を占めています。
発症のピーク年齢は10~20歳代です。
- 粘液嚢胞は市販のビタミン剤で治りますか?
- 粘液嚢胞の原因は小唾液腺の排泄管の詰まりであるため、市販薬の使用は有効でないことが多いです。
- 粘液嚢胞は悪性腫瘍ですか?
- 粘液嚢胞は、口腔粘膜の小唾液腺の良性腫瘍性疾患です。
- 粘液嚢胞はうつりますか?
- 粘液嚢胞は細菌性やウイルス性ではないのでうつることはありません。
- 粘液嚢胞は予防できますか?
- 粘液嚢胞の原因は外傷が多い為、防ぐ事ができません。ただ唇を噛んだり頬の内側を吸ったりする癖がある場合はやめましょう
今回は、悩まれている患者様も多い粘液嚢胞についてお話しました。
原因の中で、最も一般的なのは、粘膜が傷付いてしまったり、歯並びや口内炎などの口腔内の状態によって、発生しやすさが異なることが報告されています。
具体的には、歯並びが悪い人や口内炎の患者さんは、粘液嚢胞にかかりやすい傾向があるとされています。
また、唾液石がある場合にも、粘液嚢胞が発生しやすくなると考えられています。